令和4年 4月の京都観光

祇園甲部・都をどり 4月1日~24日
祇園甲部歌舞練場は耐震工事のため、南座で開催されます。詳細は祇園甲部舞会公式サイトでご確認下さい。
平安神宮・観桜茶会 4月1日~14日 8時30分~17時30分
平安神宮の桜というと八重紅枝垂桜が有名ですが、その他にも約20種類合計200本以上の桜が植えられています。桜の花の見ごろになる時期にお茶席が開催されます。
神苑入苑料:600円、お茶券:800円
宮川町・第71回京おどり 4月2日~13日
松尾大社・例祭 4月2日 10時~
 醸造祖神を祀る「酒の神様の社」の一年で最も重要なお祭りです。祭典の後、茂山社中の狂言・金剛流社中の謡曲を鑑賞することができます。
醸造祖神を祀る「酒の神様の社」の一年で最も重要なお祭りです。祭典の後、茂山社中の狂言・金剛流社中の謡曲を鑑賞することができます。
清水寺・青龍会 4月3日 14時~
法螺貝を吹き、先布令を行う「転法衆」を先頭に、行道を指揮する「会奉行」観音加持を行う「夜叉神」「四天王」が龍の前後を守護し、「十六善神」の神々が続くという大群会行の行道です。
護王神社・護王大祭 4月4日 11時~
祭神・和気清麻呂の命日で、清麻呂が道鏡の企みを防いだ故事が祭事におり込まれています。ご本殿での祭典に続き、京都御所の建礼門前で「宇佐神託奏上ノ儀」が行われます。
平安神宮・紅しだれ桜コンサート
2022年も中止
醍醐寺・太閤花見行列 4月10日
 慶長3年に行われた太閤秀吉観桜の様子を再現した行列が三宝院唐門を出て境内を練り歩きます。
慶長3年に行われた太閤秀吉観桜の様子を再現した行列が三宝院唐門を出て境内を練り歩きます。
1000本の桜が彩りを添える催しです。(雨天決行)
上賀茂神社・賀茂曲水宴 4月10日 13時~
「ならの小川」からの分水で行われる上賀茂神社の「曲水の宴」は、平安時代末期の風趣に富んだ姿を残す渉渓園で行われます。斎王代の前で、歌人によって和歌が詠まれ、冷泉家時雨亭文庫の方々によって披講されます。野点の席も設けられます。
拝観料:1,000円(お茶券付き)
鞍馬寺・鞍馬山の花供養 4月10日~24日
「雲珠(うず)」と形容される桜が山桜を中心とした鞍馬の山に咲きそろいます。(「うず」とは馬の鞍につける宝珠の形をした飾り)
東寺・正御影供 4月21日
弘法大師空海の命日にあたり、灌頂院の閼伽井に絵馬が掲げられる習わしです。この日は御影堂をご開扉し、一山の僧により勤行式が行われます。
三室戸寺・つつじ、しゃくなげ園開園 4月23日~5月15日 8時半~16時半
 宇治の“花の寺”です。つつじ2万株、しゃくなげ1千株が紫・ピンク・白の花を見事に咲かせます。例年の見頃は、ゴールデンウィーク前後です。
宇治の“花の寺”です。つつじ2万株、しゃくなげ1千株が紫・ピンク・白の花を見事に咲かせます。例年の見頃は、ゴールデンウィーク前後です。
上七軒・寿会 4月24日~30日
詳細は上七軒歌舞練場公式サイト
壬生寺・壬生狂言 4月29日~5月5日 13時~17時半
700年の伝統・重要無形民族文化財。円覚上人が布教のため唱えた融通念仏が伝わったと言われる、珍しい仏教無言劇。序盤に、「炮烙(ほうらく)割り」が演じられ、ユーモラスな手振りで、次々に落として割る様子は迫力があります。
城南宮・曲水の宴 4月29日 14時~
曲水の宴は王朝貴族の遊びを再現し、平安装束を身にまとった7人の男女が、「楽水苑」の遣水(やりみず)と呼ばれる小川のほとりに座り、川を流れ来る羽觴 (うしょう=盃を運ぶ鳥形の船)が目の前に着くまでに歌を詠み終えます。この日神苑「楽水苑」は無料公開され、苑内の平安の庭では14時より「白拍子の 舞」も行われます(雨天中止)。
得淨明院・戒壇めぐりと一初鑑賞 4月下旬~5月上旬 9時半~16時
 信州善光寺の京都別院として建立されたお寺です。善光寺同様「戒壇めぐり」ができます。本堂下につくられた真闇の戒壇を一周し、現当両益・減罪生善など如来様の功徳を得るものです。真の闇が体験できるそうです。一初はアヤメ科の花で、アヤメ類の中で一番早くに咲くことから名づけられたと言われています。
信州善光寺の京都別院として建立されたお寺です。善光寺同様「戒壇めぐり」ができます。本堂下につくられた真闇の戒壇を一周し、現当両益・減罪生善など如来様の功徳を得るものです。真の闇が体験できるそうです。一初はアヤメ科の花で、アヤメ類の中で一番早くに咲くことから名づけられたと言われています。
メニュー
季節別おすすめスポット
新着情報&ブログ
過去の記事
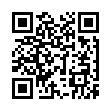
聖京都観光タクシー
モバイルサイト





